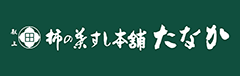奈良市の東南山麓、菩提仙川に沿って、苔むした石垣ともみじの参道を登りつめると菩提山正暦寺がある。現在の清酒造りの原点は、ここ正暦寺で造られていた僧坊酒に求めることができる。この僧坊酒は「菩提泉」・「山樽」などと呼ばれ、時の将軍、足利義政をして天下の銘酒、と折紙をつけさせたと「蔭涼軒日録」に記されている。時代はくだり、一五八二(天正十)年五月、織田信長は、安土城に徳川家康を招いて盛大な宴を設けた。この時、奈良から献上された「山樽」は、至極上酒であったらしく「多聞院日記」に「比類無シトテ、上一人ヨリ下万人称美」したとある。
本来、寺院での酒造りは禁止されていたが、神仏習合の形態をとる中で、鎮守や天部の仏へ献上する御酒として自家製造されていた。そのため、宗教団体として位置づけられながらも、荘園領主として君臨していた寺院では、諸国の荘園から納められる大量の米と、酒造りに必要な広大な場所、人手、そして、清らかな渓水・湧き水などの好条件に恵まれ、利潤を目的とした酒造りをはじめるようになった。中でも、正暦寺の僧坊酒は、醱酵菌(酒母・もと)を育成し、麹米(こうじまい)・掛け米ともに精白米を使う諸白酒(もろはくしゅ)を創製したという点で、酒造史の上で高く評価されている。
清酒造りにおける酒母(もと)の役割とは、雑菌を無くし、もろみのアルコール醱酵をつかさどることにある。単に糖液で培養した酵母菌で酒を造るならば、乳酸菌・バクテリアなどの雑菌が殺されることなく、もろみが腐りやすくなる。
しかし、正暦寺で創製された酒母(もと)、即ち「菩提もと」は、酸を含んだ糖液で培養するため、その酸によって雑菌が殺され、しかも、アルコールが防腐剤の役割を果たすという巧妙な手法がとられており、これは、日本酒造史上の一大技術革新であった。
こうして、蒸し米と米麹と水からまず酒母(もと)を育成し(酒母仕込み)、酒母が熟成すると米麹・蒸し米・水を三回に分けて仕込む(掛け仕込み)、いわゆる三段仕込みの原型が出来上がった。この諸白酒は、後に火入れ殺菌法なども取り入れられ、仕込みも三段仕込みから四段・五段仕込みへと発展し、「南都諸白(なんともろはく)」の名で親しまれ、十七世紀の伊丹諸白の台頭まで、一世を風靡し、奈良酒の代名詞ともなった。
菩提山正暦寺提供
(上記の文章部分は平成26年文化交流会の講演で配布された資料の中にあるものです。)